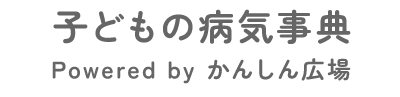2025/9/29 公開
国立研究開発法人 国立成育医療研究センターの島袋先生に
「赤ちゃんがミルクを飲まない」を中心にお話を聞いていきたいと思います。
後編では、家庭での観察ポイントと受診の目安、受信時の行動と情報共有、親御さんへのメッセージを紹介します。
島袋 林秀 先生 プロフィール

島袋林秀(しまぶくろ りんしゅう)先生
国立成育医療研究センター総合診療部 診療部長
小児科医、博士(医学)、病院管理学修士
1998年産業医科大学 医学部卒業。
東京医科歯科大学(現東京科学大学)大学院医療管理政策学(MMAコース)、同大学院医歯学総合研究科修了。
大学および北九州市八幡病院救命センター小児科などで大学関連病院、国立成育医療センター(現国立成育医療研究センター)新生児科で研鑽後、横浜労災病院新生児科副部長、聖路加国際病院小児科医幹、副医長を経て現職。
聖路加国際大学大学院では臨床教授として教育にも従事。
目次
家庭での観察ポイントと受診の目安
家庭で最初に注目してほしい「いつもの様子との違い」は何ですか?
次の点を日常と比べて観察してください。
- 活気・機嫌
- 泣き方の張りや持続
- 抱いたときの体の緊張感
- 顔色(蒼白など)や手足の冷たさ
- 呼吸(速さ・胸の陥没など)
- 発汗の様子
親御さんは最も長く赤ちゃんと過ごしています。
「なんとなく違う」という感覚を大切に。昨日まで元気に飲んでいたのに今日は違う。
その違和感は重要です。

「飲みたいのに飲めない」のか「飲む気力がない」のか、どう見分けますか?
飲みたいのに飲めない:乳首に向かう意欲はあるが、吸啜や嚥下が不十分/途中で疲れるなど、協調運動の問題が疑われます。
飲む気力がない:乳首に向かう意欲自体がありません。乳首をくわえても反応が鈍い、吸う力が弱い、全身的に元気がない、普段より反応が悪い。全身状態の低下が疑われます。
「なんとなく違う」を客観的に伝えるための観察ポイントは?
次のような点を日頃から把握しておくと役立ちます。
- 排泄(おしっこ・うんち)の回数や性状
- 体重の増え方
- 機嫌・泣き方・睡眠(時間/入眠の様子)
- 授乳時間がいつもより長い
- 飲む途中で疲れる
- 寝てばかり/いつもより不機嫌
厳密な数字管理までは不要ですが、「普段と違う」と感じるポイントを覚えておくと、受診時の大切な手掛かりになります。
家族みんなで赤ちゃんの変化に気づくため、何を共有すべきですか?

育児は一人で抱えないこと。
母親が気づいたことを父親や祖父母と共有し、園に通っていれば先生とも情報交換を。
授乳量や時間だけでなく、「今日は少し元気がない」「泣き方が弱い」など小さな違和感も言葉にして共有しましょう。
複数の目で「普段と違う」を確認できる関係が、早期の受診判断につながります。
受診時の行動と情報共有
「様子見」と「相談・受診」の目安は?
家族は子どもを“線”で継続的に見ており、微細な変化に敏感です。
「いつもと何か違う」という感覚が半日〜1日続くときは、相談・受診を検討ください。
夜間・休日でも重症感があれば救急外来へ。迷う場合は地域の小児救急電話相談 #8000 を活用してください。
親の感覚を大切にし、「何となく変」を否定しないこと。
結果的に異常がなくても「安心できた」で良いのです。
ミルクを飲まない以外に、迷わず受診すべき“危険サイン”は?
「飲まない」に加え、以下の全身症状があるときは早急な受診を検討してください。
- 38.0℃以上の発熱(特に生後3か月未満で、環境調整をしても持続する)
- 顔色不良・チアノーゼ(唇や顔が青い)
- 呼吸困難(呼吸数増加、胸や腹の陥没呼吸)
- けいれん
- ぐったりしている、反応が鈍い/活気がない
受診のタイミングと医療機関の選び方は?
受診時に医師へ伝えるべき情報は?
「いつから」「どのように変わったか」を具体的にお伝えください。
- 泣き方
- 寝方
- 飲み方
- 排泄
- 体重の変化
- 発熱
- 呼吸苦
などの随伴症状などです。
母子健康手帳やおくすり手帳があると判断がよりスムーズです。

夜間や休日で緊急性の判断に迷うときの行動指針は?
次を確認しましょう。
1. 顔色(蒼白・チアノーゼ)
2. 呼吸(速い/陥没呼吸)
3. 反応性(呼びかけへの反応)
4. 排尿(半日以上おしっこが出ない
「おかしい」と感じたら #8000 に相談、危機的なら119番へ。
夜間でも「いつもと違う」が続くときは、ためらわず受診・相談を。
問題がなければ「安心できた」で大丈夫です。
地域で相談できる窓口の活用について
#8000(小児救急電話相談) は地域のコールセンターにつながり、対処法や受診先の助言が受けられます(対応時間は地域で異なります)。
自治体の子育て支援窓口、保健センター、地域の相談窓口も積極的に活用し、悩みを一人で抱え込まないでください。
親御さんへのメッセージ
赤ちゃんがミルクを飲まないと、とても不安になります。
けれど、それが必ずしも重大な病気を意味するわけではありません。
日々の小さな変化に気づき、迷ったら早めに相談してください。育児は一人で抱えるものではなく、家族や地域の医療・支援がともに支えます。
赤ちゃんの変化をいちばんよく知っているのは、毎日一緒に過ごす親御さんです。
その感覚はとても大切で、しばしば正確です。私たち医療者の役割は、病気かどうかを判断することであって、親の感覚を否定することではありません。
どうか自信を持って、安心して子育てを続けてください。
〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2丁目10−1
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
総合診療部 総合診療科 診療部長
島袋 林秀 先生
インタビュー・作成
一般財団法人 日本患者支援財団 運営事務局