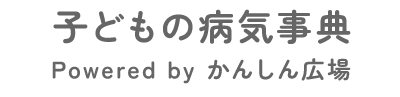2025/9/29 公開
国立研究開発法人 国立成育医療研究センターの島袋先生に
「赤ちゃんがミルクを飲まない」を中心にお話を聞いていきたいと思います。
前編では、島袋先生のご経歴や紹介、赤ちゃんがミルクを飲まない時の原因などを紹介します。
島袋 林秀 先生 プロフィール

島袋林秀(しまぶくろ りんしゅう)先生
国立成育医療研究センター総合診療部 診療部長
小児科医、博士(医学)、病院管理学修士
1998年産業医科大学 医学部卒業。
東京医科歯科大学(現東京科学大学)大学院医療管理政策学(MMAコース)、同大学院医歯学総合研究科修了。
大学および北九州市八幡病院救命センター小児科などで大学関連病院、国立成育医療センター(現国立成育医療研究センター)新生児科で研鑽後、横浜労災病院新生児科副部長、聖路加国際病院小児科医幹、副医長を経て現職。
聖路加国際大学大学院では臨床教授として教育にも従事。
目次
島袋先生のご専門とご経歴
先生のご専門とご経歴について教えてください。
小児科専門医として、新生児医療・小児救急・臨床遺伝学を主な分野に、国立成育医療研究センター総合診療部を拠点として幅広く診療しています。
NICU(新生児集中治療室)での経験を基盤に、一般小児診療、専門診療科との連携、健康診査などの小児保健、子ども病院を活動拠点に領域の枠にとらわれず「子どもの総合医」として関わっています。
また、聖路加国際大学大学院の臨床教授として、染色体や遺伝子に変化を持つ子どもの見方や、保護者への寄り添い方を医療職に伝えています。
小児の長距離航空機搬送に関わっていた時期もあります。
現在はドクターヘリ等が普及していますが、当時は民間航空機の定期便で新生児・小児を搬送することがあり、医療者と航空会社の間で生じる調整・摩擦の解消に努めました。
周囲からは「足がつかない仕事」と揶揄されることもありました(笑)。
どのような経緯で現在の専門分野を診るようになったのでしょうか?
学生時代から教育に関心がありました。
「入院しても『おめでとう』と言える」周産期医療に魅力を感じ、産婦人科と小児科で迷いましたが、
最終的には小児科を選択しました。
教育や社会問題など、医療の枠を超えて子どもに関われると感じたからです。
小学校や高校で「命の授業」をした経験もあります。
授業では赤ちゃんの多様な表情の写真を見せ、「この子はいま何を考えていると思う?」と討議することもしました。
年齢が上がるほど理屈で“正解”を求めがちですが、公立工業高校の授業ではちょっとやんちゃな生徒たちが赤ちゃんの表情から素直に受け取った感性に強く感銘を受けました。
こうした教育への関心は、診療で親子に向き合う姿勢にも生きています。

これまで診療されてきたお子さんはどのような方々ですか?
超早産児や新生児仮死、染色体・遺伝子に変化を持つお子さんまで、多様な新生児を診てきました。
新生児医療と並行して小児救急医療にも長年携わり、救急外来を受診する多くの小児を診療してきました。
聖路加国際病院では、歴史ある乳幼児健康診査「ウェルベビークリニック」に関わり、病気の有無にかかわらず「社会の中で健やかに成長すること」を支える小児保健の大切さを学びました。
「ミルクを飲まない」と聞いたとき、どのような場面が思い浮かびますか?
「飲まない」理由は実に多様です。
軽い環境要因から重い疾患までさまざまです。哺乳は赤ちゃんにとって大きな運動負荷で、成長と健康を映す重要な指標です。
だからこそ「なぜ飲まないのか」を丁寧に見極め、保護者とともに健やかな育児へつなげることが小児科医の役割だと考えています。
このテーマにまつわる印象的なエピソードを教えてください。
成人診療科の同僚に「子どもは自分の具合を言えないから大変だね」と言われた際、
「大人は嘘をつくけれど、赤ちゃんは全身で正直に表現してくれる。誇張もごまかしもない」と答えました。
赤ちゃんは言葉の代わりに、表情・呼吸・哺乳の仕方でサインを送ります。
そのサインをどう受け止め、どう対応するかが小児科医の力量だと思っています。
「ミルクを飲まない」ときの基本的な考え方
赤ちゃんがミルクを飲まない原因にはどのようなことがありますか?
哺乳には、
- 吸啜(きゅうてつ=吸う動き)
- 嚥下・呼吸の協調
- 姿勢
- 筋緊張
どれか一つでもうまく働かないと十分に飲めません。
解剖学的な異常だけでなく、筋の協調、感覚過敏や心理的要因、環境要因などが背景にあることも多いです。

月齢や発達によって「飲み方」は変わりますか?典型的な変化を教えてください。
発達とともに哺乳の様子や量は変化します。
- 新生児期:反射が未熟で授乳に時間がかかり、途中で疲れてしまうことがあります。
- 生後3〜4か月頃:周囲への関心が高まり、中断や「遊び飲み」が増えます。
- 生後5〜6か月以降(離乳期):自然にミルク量が減り、体重増加も徐々に緩やかになります。
「飲まない=異常」とは限らず、発達に伴う自然な変化も多くあります。
体調不良や病気でミルクの飲み方が変わることはありますか?
あります。哺乳は赤ちゃんにとって最も負荷の大きい運動の一つです。
体調が悪いと、不機嫌、顔色不良、途中で飲めなくなる、呼吸が苦しそうになるなどのサインが現れます。
これは全身状態の変化を示す重要な兆候です。
後編では、家庭での観察ポイントと受診の目安、受信時の行動と情報共有、先生からのメッセージを紹介します。
詳細は下記からご覧ください。
〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2丁目10−1
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
総合診療部 総合診療科 診療部長
島袋 林秀 先生
インタビュー・作成
一般財団法人 日本患者支援財団 運営事務局